高専に入学できたのはいいけれど、専門的な授業のスピードについていけなくなり、不安を感じている学生や保護者も多いのではないでしょうか。
「勉強についていけない」=「塾に行って挽回する」
と考えがちですが、高専の学習内容は一般的な高校とは大きく異なるため、通常の学習塾では対応が難しいのが現実です。
- 一度のつまずきが命取りに
-
特に数学、物理、専門科目は、前の単元が分かっていないと先に進めません。
つまずきを放置すると、授業はますます分からなくなり、単位を落としてしまう可能性が高まります。
- 留年・退学のリスク
-
単位不足による留年はもちろん、勉強へのモチベーションを失い、退学してしまうケースも少なくありません。子どもが高専生活に絶望してしまう前に、早めの対策が不可欠です。
特に数学や物理、専門科目は、一度つまずくと後々まで響きます。わからないところは早め解決おきましょう。特に低学年のうちは注意が必要です。
幸い、多くの高専では学生が勉強で困らないように、さまざまな学習支援制度を設けています。
本記事では、高専生が勉強でつまずいたときに利用できる学校の支援制度と、自分たちでできる効果的な学習方法を紹介します。
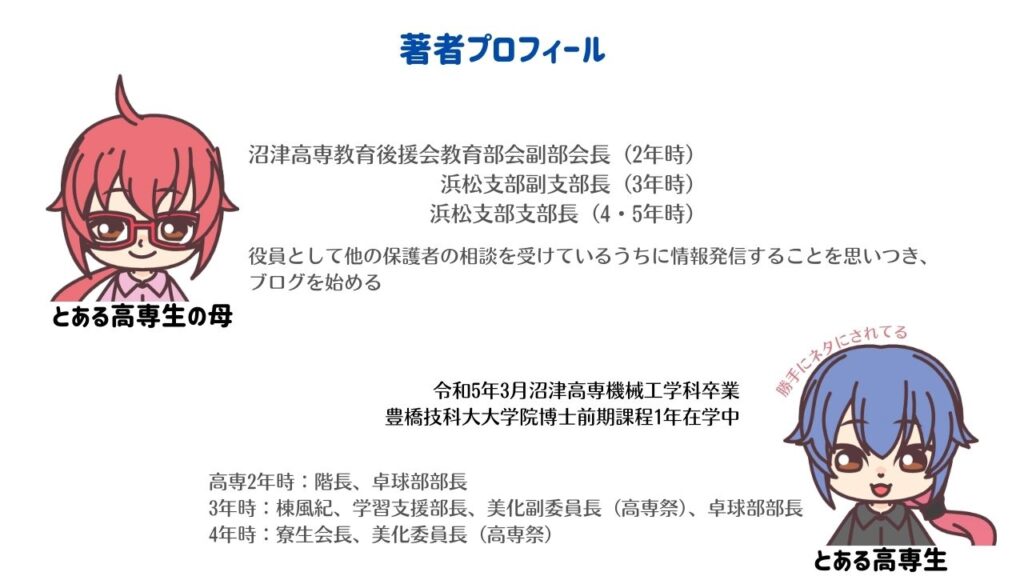
高専が提供する学習支援制度

高専では、勉強についていけない学生を減らすために、各校独自の学習支援を行っています。
その名称や運営方式はさまざまですが、主に以下の4つのタイプに分けられます。
- 放課後セミナー方式
- 専攻科生によるメンター制
- 先生によるマンツーマン指導
- 学生たちによる相互互助会
どの方式を採用しているのかは公式サイトで公開されていますので、志望する高専あるいは通っている高専の公式サイトをご確認ください。
設置されているのであれば積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
先生による補講・セミナー形式
講義の延長として、先生が苦手な学生向けに補講やセミナーを開催する方式です。
特定の科目に特化したコースが複数用意されていることが多く、学生は自分の苦手分野に合わせて受講できます。
専攻科生・上級生によるメンター制度
専攻科生や優秀な上級生が、下級生の勉強をマンツーマンでサポートする制度です。
年齢が近く、つい最近まで同じ授業を受けていた先輩から教えてもらうことで、学生はより気軽に質問でき、分からない部分をスムーズに解決できます。
個別指導・学習支援室
学校内に「学習支援室」や「学習相談室」といった形で、学生がいつでも質問に行ける場所を設けている高専もあります。
沼津高専では図書館に設置された「Fujiカフェ」では先生が当番制で常駐しており、数学や物理、専門科目などの質問の個別で教えてくれる体制が整えられています。
学生主体の相互学習会
寮生活を送る高専生に多いのが、学生同士で教え合う「学習互助会(高専により名称は異なる)」です。
成績優秀な学生が下位の学生に勉強を教えることで、教える側も教えられる側も理解が深まるというWin-Winの関係が生まれます。
学生たちは友人同士教え合うのが、一番効果的と感じているようです。しかし、
学生同士教え合うのもいいけど、間違って理解されるのも後々困るので、できれば担当の先生に聞いてほしいのが本音なんです。
先生は学生同士で教え合うよりも、「Fujiカフェ」や研究室に聞きに来てほしいと思っています。
夏の勉強合宿
できるできないに関わらず、上級生が下級生たちに勉強を教える勉強会。
下級生の十本刀(下位10人)は教えられる側として強制参加、上級生の十賢(上位10人)は教える側として強制参加。
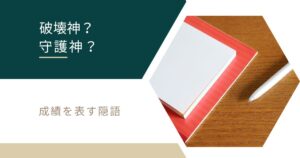
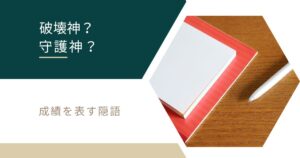



いくら成績が良いからって、俺、人に教えるの苦手なんだけどーーっ!
と成績上位者からはこのような愚痴が聞こえてきますが、家庭教師や塾講師のバイトにその経験が生きているようなので、まんざらでもないようです。
沼津高専寮の学習支援部(旧マテカ)
成績上位者が成績下位者に勉強を教える週一の勉強会です。



学習支援部の活動ためにこっちは一生懸命準備しているのにさ、(成績下位者の)出席率が悪いんだよね……。
と、学習支援部長をしていた頃、娘はよくそんなことをボヤいていました。
分かりやすく教えるために解説動画を作成したり、頑張っていたようです。人に教えることは、教える側にとってもいろいろと勉強になります。
留年・退学を防ぐために、学生自身ができること
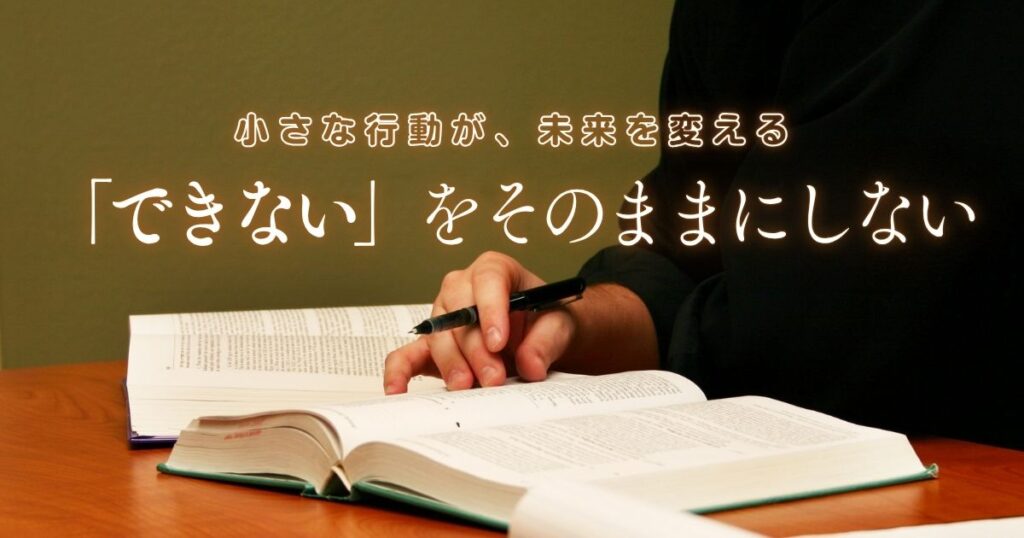
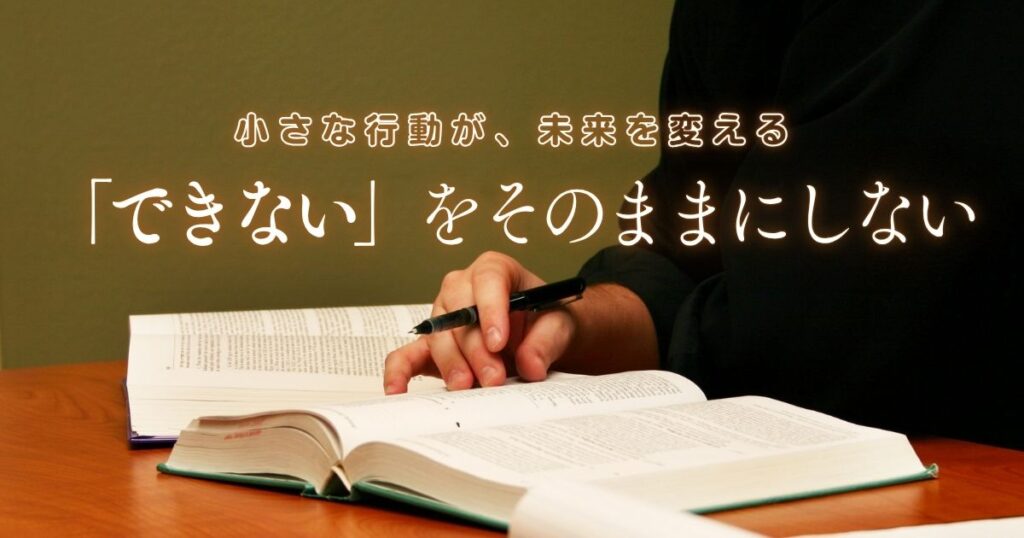
高専の学習支援制度を利用するだけでなく、学生自身が主体的に動くことも非常に重要です。
1. 友達や先輩に聞く
分からないことがあった時、まず頼れるのは身近にいる友達や先輩です。
ほとんどの高専生は、友人や先輩に質問することで、分からないことの9割を解決しているようです。
2. 先生に聞きに行く
それでも理解できないときは、担当の先生に聞きに行きましょう。
一人で行くのが難しいのであれば、友達同士誘っていけば、行きやすいのではないでしょうか。
分からない学生を放っておくことはできないからね。理解できなかったときは、聞きに来てください。
先生側も、学生の「ここが分からない」は、より分かりやすい授業にするためのフィードバックになります。
親としてできることは?
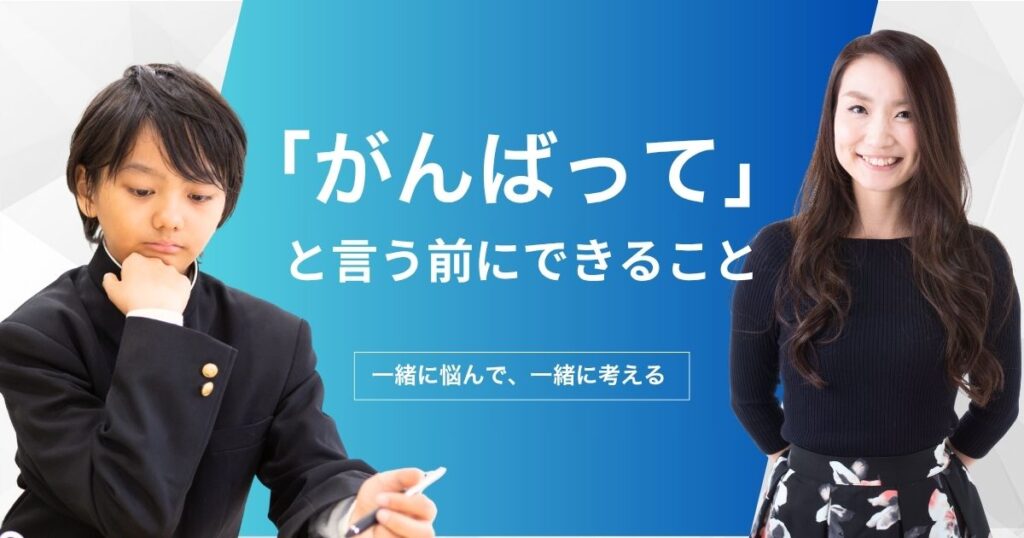
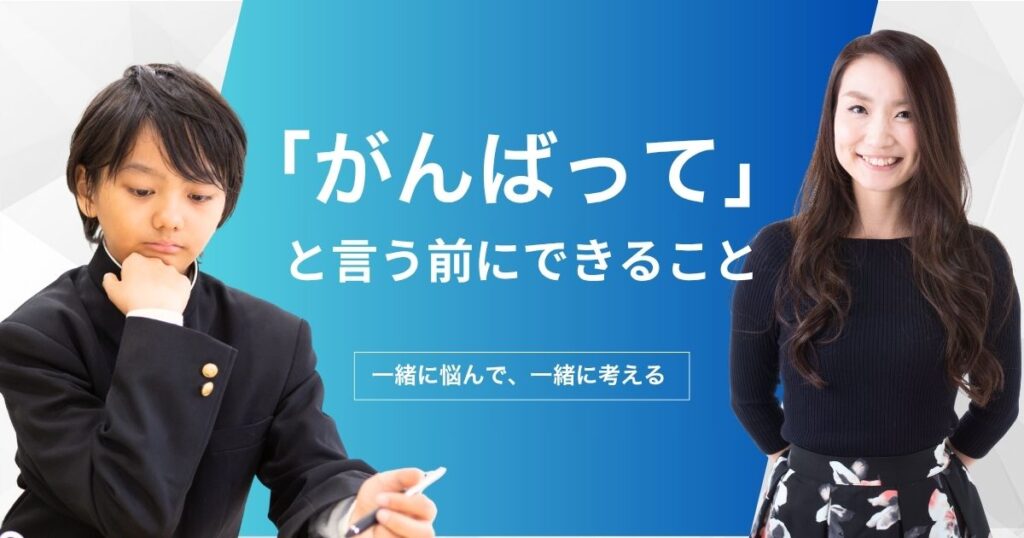
子どもが「勉強が分からない」と言った時に、「なんとか頑張りなさい」では解決しません。
保護者としては、
- 学校の支援制度を調べて利用を促す
- 本人が先生に聞けないなら、友人と一緒に行くよう勧める
- それでも難しいときは、高専専門塾に相談する
というステップで、「勉強の悩みを放置しない環境」を一緒に考えていきましょう。
3. 高専の学習に特化したサポートを受ける
友人や先生にわからないことを聞くのは勇気のいることですし、その裏には「自分がバカだと思われたくないし、恥ずかしい」というのもあるかもしれません。
高専の学習は、高校とは異なる独特の進み方と難易度があるため、一般的な塾では対応できません。
特に、一般科目(数学や物理)と専門科目のバランスを取るのが難しいと感じる学生も多いでしょう。
そういった学生には、第三者である高専専門塾のサポートを受けるのも一つの方法です。
高専専門塾「ナレッジスター」では、高専のカリキュラムを熟知したプロの講師が、一人ひとりの学習状況に合わせて最適な指導を行います。
定期試験対策やつまずきやすい単元の克服など、高専生活を成功させるための強力なパートナーになります。
\高専生活の不安、専門家に無料で学習相談しませんか?/
中でも「高専数学」に苦戦する子どもにとっては、ナレッジスターのようなサポートは強力な味方になります。
高専の悩みを専門家に話してみませんか?
高専の学びは一人で抱え込まなっことが大切!
- 高専の授業は難易度もスピードも高校とは違う
- 早めの対策と学習支援の活用が留年・退学を防ぐカギ
- それでも難しいなら、“高専のプロ”に相談を!
勉強で悩む高専生が、安心して学べる環境づくりのために、保護者としてできることを一つずつ実行していきましょう。
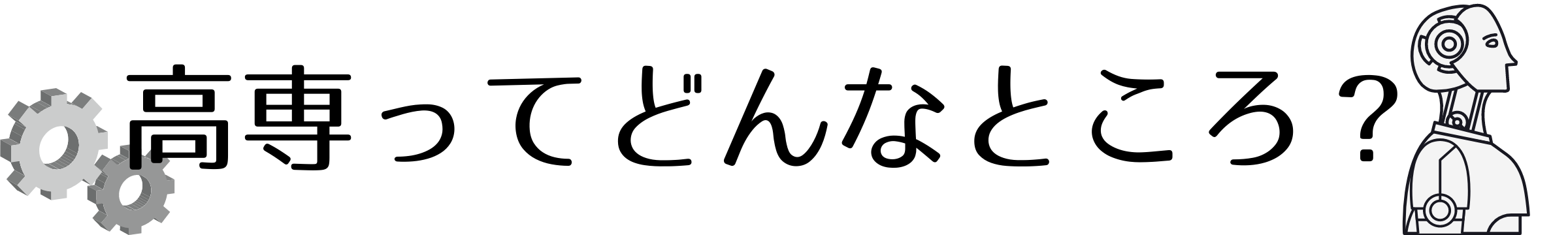

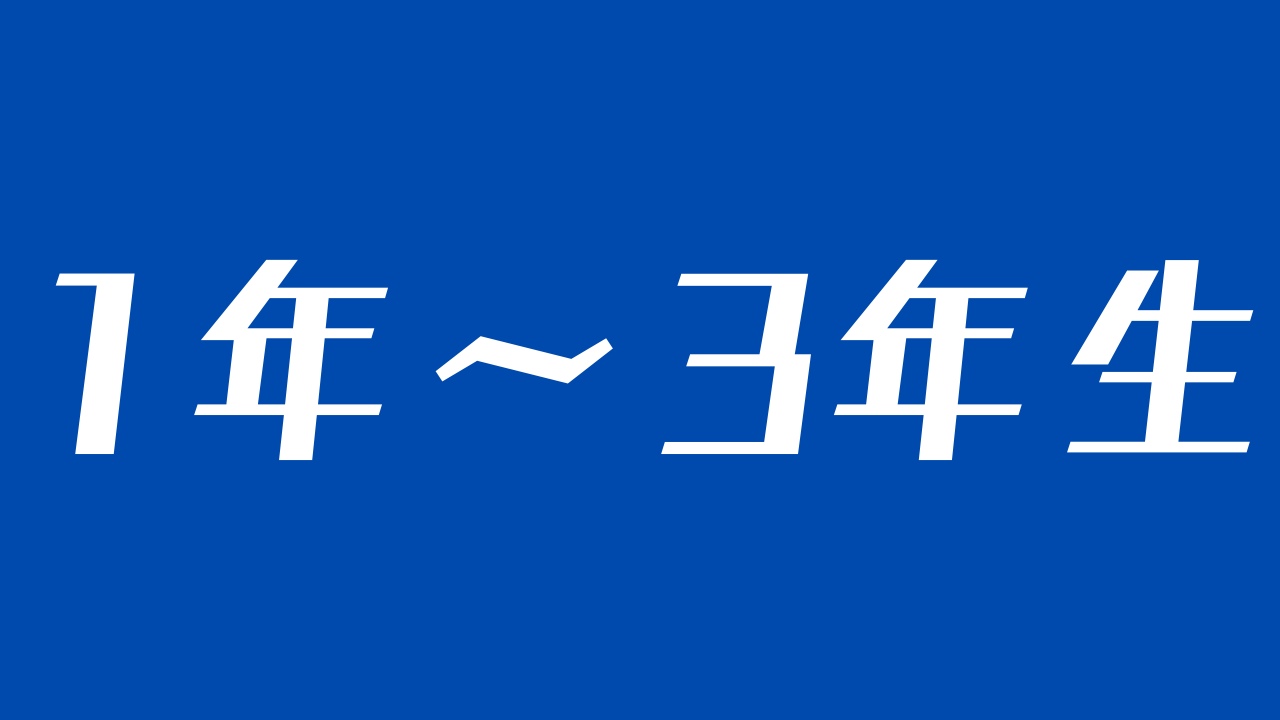


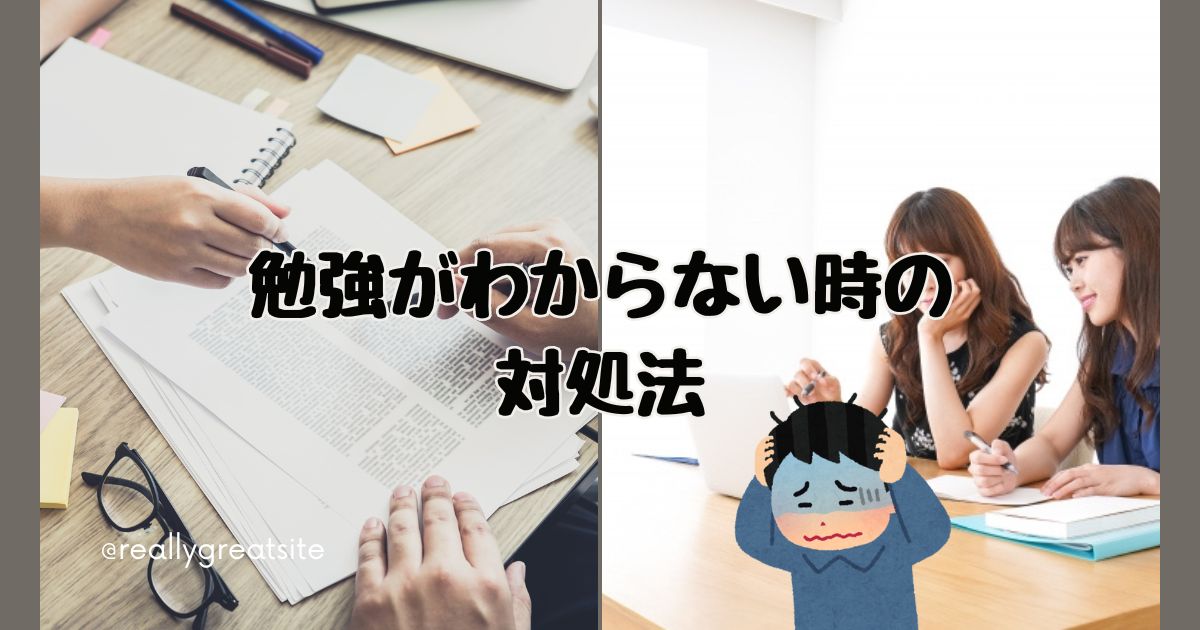





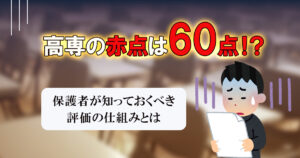



コメント