 とある高専生の母
とある高専生の母高専って大学に近いイメージだから、保護者面談なんてないと思っていたけど、高校と同じように保護者面談があってビックリ
そんな風に考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、高専にも普通高校と同じように、二者または三者面談があります。
一方で、大学にはこのような面談制度は、なにか特別な理由でもない限りありません。
談で話す内容は、高校とそれほど大差ありません。
主に、成績や生活態度、進路について。面談時間は、学年やお子さんの状況によって大きく変わります。
| 短時間で終わるケース | 時間が長くなるケース |
|---|---|
| 成績優秀 進路が明確 特に相談事なし | 単位不足で留年の危機 進路未定 学校への相談事項あり |
本記事では、我が家の経験した1年生から5年生までの保護者面談のリアルな様子と、面談を通じて感じたポイントを紹介いたします。
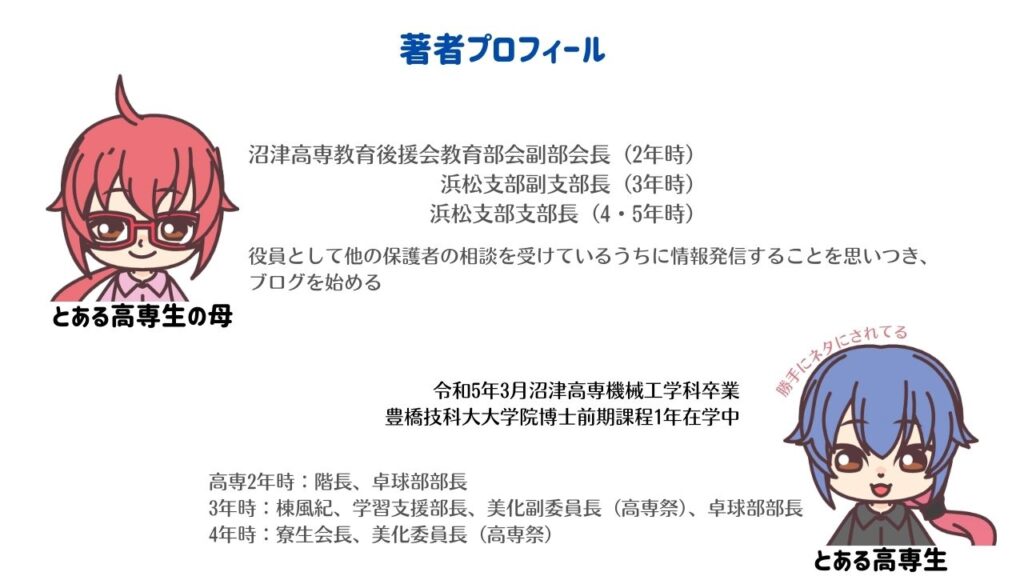
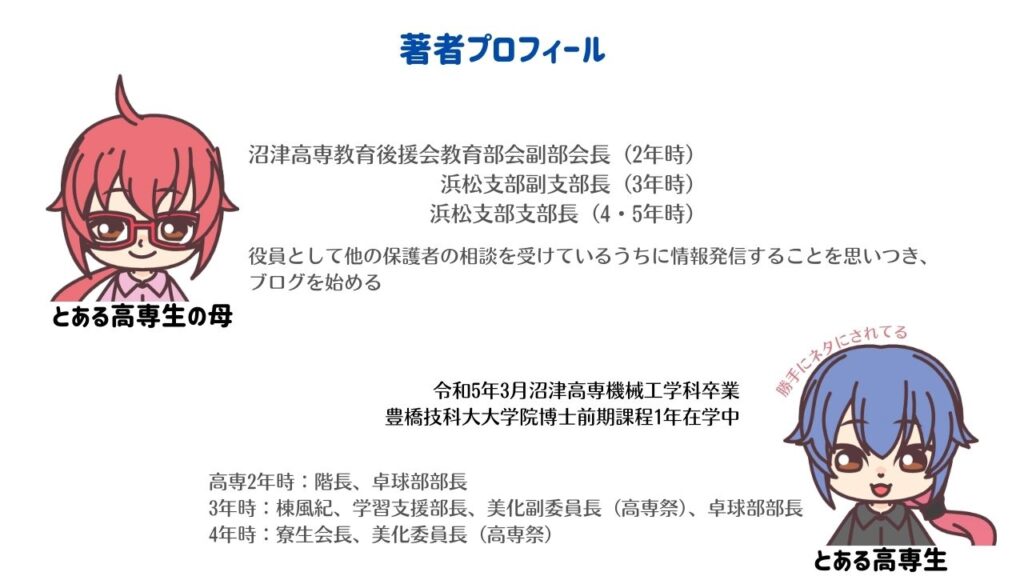
保護者面談で話し合われること:学年による違い


基本的に、保護者面談で話される内容は、一般高校の三者面談と大差ありません。
しかし、学年や学生本人の成績、生活態度、そしてもちろん担任の先生によって、その内容は大きく左右されます。
低学年のうちは成績や生活態度、高学年になれば進路に関する割合が当然ながら多くなります。
【重要】親子で進路の方向性は一致させておこう!
低学年のうちは中退する場合を除き、それほど深く考える必要はありません。
しかし高学年になると、進路の話題を避けて通るわけには行きません。



僕は大学院まで進学して、企業の開発職に就きたい



何言ってるの?高専を卒業したら就職するって約束だったじゃないの!
そうならないためにも、事前に親子でしっかりと話し合い、少なくとも「進学」か「就職」か、大まかな方向性だけでも一致させておくことが大切です。
企業名や大学名まで具体的に決めておく必要性はありませんが、方向性の共有だけは最低限しておきましょう。
我が家の保護者面談体験談:学年ごとのリアルレポート


ここでは、我が家が実際に体験した保護者面談の様子を、学年ごとに紹介します。
1年生:話題の中心は部活動
1年生のときの担任の先生は、娘が所属する卓球部の顧問の先生でもありました。
そのため、面談内容はほぼ部活動一色。特に夏休み中に行われる全日本ジュニア選手権大会の地区予選会があるため、ほぼその話をしていました。



これがこの会場の駐車券になります。本当は大会役員にしか配られないんですけどね、遠方なので特別に……。
と体育館の駐車券をもらいました。
夏休みに部活動が行われても、遠方から通う寮生は、長期休暇中の部活動への参加が難しいという実情もあり、練習環境の確保に苦心している話などもしました。





ツテとコネをフル活用して、高校の部活動やクラブにお邪魔させてもらって、なんとか練習できるようにしています。
といった具合で、成績に関する話は特にありませんでした。
2年生:まさかの5分面談!?
2年生のときの面談は、拍子抜けするほどあっという間でした。
娘さんは成績も問題ないですし、部活も頑張っているようなので、特に何も心配ありません。わざわざ遠くから面談に来ていただく必要もなかったくらいですよ。ハッハッハッハ!
4年生はさすがに面談をしないといけませんが……。
って、えーーーーっ!?!
面談時間は、おそらく5分もなかったと思います。
この数分の面談のために、往復6時間かけて面談に向かったんですけどね。
とはいえ、下記のようなメリットがあるので、私は話すことが特になくても面談には行くようにしています。
- 担任の先生がどんな方なのかを直接知る機会
- 子どもからの話ではわからない学校の様子がわかる
先生と直接話すことで、子供が話す先生の人物像への理解も深まります。
3年生:進路の意思確認
3年生の面談では、部屋に入るなり先生に、
なんで来たん?特に話すことないんだけど……、どうしよう……
という顔をされました。
3年生になると、卒業後の進路について具体的に考え始める時期です。
この時点では、「進学」か「就職」のどちらにするのか、ざっくりした方向性だけで大丈夫。4年生からは、この希望に応じて、進路指導の方針が変わってきます。
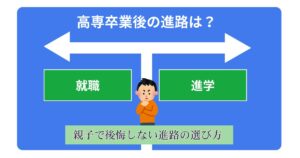
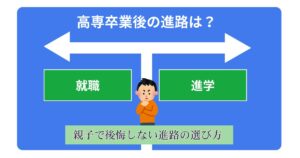
進学希望でよろしいのですね。今の成績を維持すれば、推薦も狙えるかもしれません。(次期寮生会長に決まって)寮も頑張っているみたいですしね。
今回も面談時間は5分程度。進路の確認程度で終わりました。
ただ、私の前の人は30分以上、その前の人も20分ぐらい話していたため、かなり待たされました。
いざ自分の番になって、長時間の面談になるかも知れないと覚悟して面談に臨むと……、今回もあっけなくすぐ終わり、拍子抜け。
面談後、娘と合流。



面談自体は5分もなかったけど、前の人と、前の前の人がものすごく長くてさ~
と、話しながら名簿で前の学生の名前を指すと



あ~~、そいつなら長いわ。めっちゃ納得!
留年の危機にある人や退学を希望する人の面談は、一般的に長くなる傾向にあります。
もちろん、留学など学校に相談したいことがある場合も、もちろん長くなります。
4年生:オンライン面談と進路相談
コロナ禍の影響もあり、希望者はZoomまたはTeamsを利用したオンライン面談か、対面での面談を選ぶことができました。
近隣の学生は対面を、遠方者はほぼ全員オンライン面談を選んでいるようでした。



浜松から沼津まで行くのは大変なので、我が家は迷わずオンライン面談
対面であれば沼津までついて来なかったであろう娘も、Teamsでの面談であったため一緒に面談に参加。
ITが苦手な人が多い機械工学科の中にあって、ITに比較的明るい方だったことが幸いしたようです。



電気工学科の友人は、オンラインなくて対面のみだったって言ってた
オンライン面談の対応をしてくれるかどうかは、担任の先生によります
面談内容は、主に進路について。
「進学」か「就職」か。
できることなら大学の研究室まで調べて、進学先を決めると良いよ
というアドバイスを頂きました。
相変わらず、面談自体はさらっと終わりました。
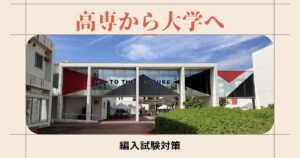
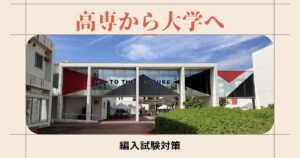
5年生:進路決定の最終確認(面談は4年生の春休み)
5年生の面談は、新学期が始まってからではなく、4年生の3月、春休み期間中に行われました。
なぜ5年生の面談が4年生の春休みに行われるのかというと、下記の理由からです。
- 大学編入試験の願書提出が早いところでは5月から始まるため、すぐに準備を始めなければならない
- 就職活動も、早いところでは4月ごろには内々々定がでる
新学期が始まってからでは手遅れに成ってしまう可能性があるため、5年生にもまだなっていない4年生の春休みに行われます。
4年生の春休み(3月)に面談が行われますが、面談する先生は5年生の担任になる先生です。そのため、先生も学生も、お互いのことをよく知らない状態での面談です。



まだ5年生になっていないのに、面談予定表を見ると、誰ができなかったのか、分かっちゃうんだよね。
面談では、進路について親としてどの程度関わるつもりか、という意向確認がありました。
- 親と学生、先生の三者で話し合って決める
- 学生と先生の話し合いのみで決めても構わないのか
我が家の場合、



本人と先生の話し合いのみで決めちゃっていいですよ
本当に良いんですか?
と念を押されました。親として何か相談されたらアドバイスはしますが、子どもの人生ですし、親があれこれ口を出すような年齢でもありません。
法律的にもすでに大人。
親元を離れて暮らしているので、そもそも子どもの興味が今現在何に興味を持っているのか、正直なところ親よりも先生の方がよくご存知なのではないかとも思っています。
大学に進学して、何をしたいか決めました?



寮の仕事(良性会長)が忙しすぎて、まだ何もできてません。これから調べます
寮生会長のしごとから解放されたのは、4年の2月。3月は寮を出て一人暮らしをするための準備に忙殺され、大学編入に向けた活動は手つかずの状態。
本当は、大学の研究室まで調べて、どこの大学に進学するのか、とっくに決めていなければいけない時期です。
しかしコロナ禍で大学のオープンキャンパスも軒並み中止となり、なかなか興味を持つきっかけを掴めなかったのかもしれません。



親がもうあれこれ言うような年齢じゃないし、相談には乗るけど、最終的に決めるのは自分だからね
と娘には伝えました。協力は惜しみませんが、決断するのは娘自身。
時期的に遅いのは承知の上で、第一志望から第三志望まで、大学にするのか高専専攻科にするのか、推薦を狙うのか、締め切りまで時間がない中で決断を迫られました。
数日後



何とか適当に決めて出した
もし、「三者で話し合って決める」を選択した場合、もっと頻繁に面談が行われるのでしょうか?
実際に「何度も先生と話し合って進学先を決めた」という話をしていた保護者の方もいらっしゃいました。
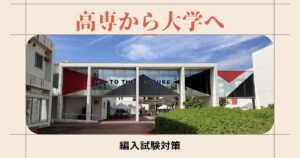
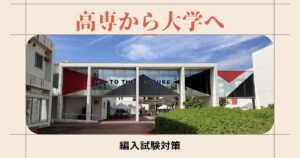
まとめ:高専の保護者面談を有意義なものにするために
今回ご紹介したように、高専の保護者面談は年次ごとに話題や意味合いが大きく変わります。
成績や生活態度だけでなく、特に高学年になると生徒の将来に直結する進路について、学校と家庭が情報を共有し、連携を深めるための重要な機会です。
面談時間は学生の状況によって大きく変わりますが、短い時間であっても、担任の先生と直接顔を合わせて話すことで得られるものは少なくありません。
- 子どもからの情報だけではわからないことが見える
- 学校での様子をうかがい知ることができ、短時間でも安心考えられる
先生との会話から得られる安心感や気づきは多く、特に進路選択のタイミングでは貴重な機会です。
そして何よりも大切なのは、面談の前に親子でしっかりとコミュニケーションを取り、進路に対する考えや希望を共有しておくことです。
これから高専の保護者面談を控えている方々にとって、少しでも参考になれば幸いです。
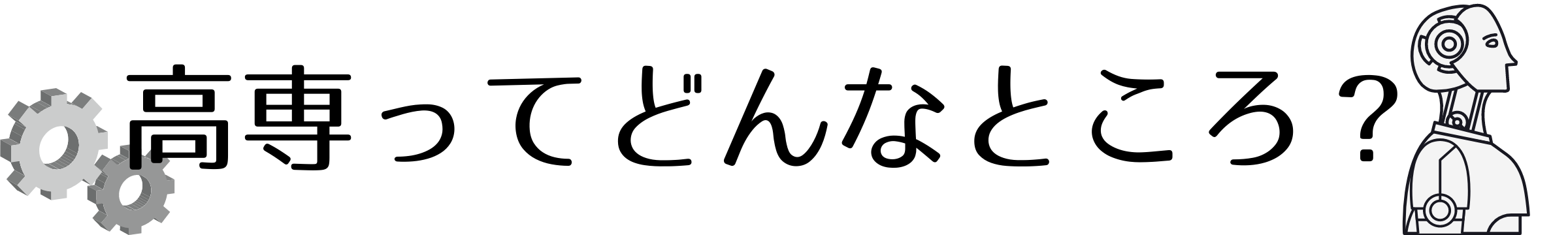

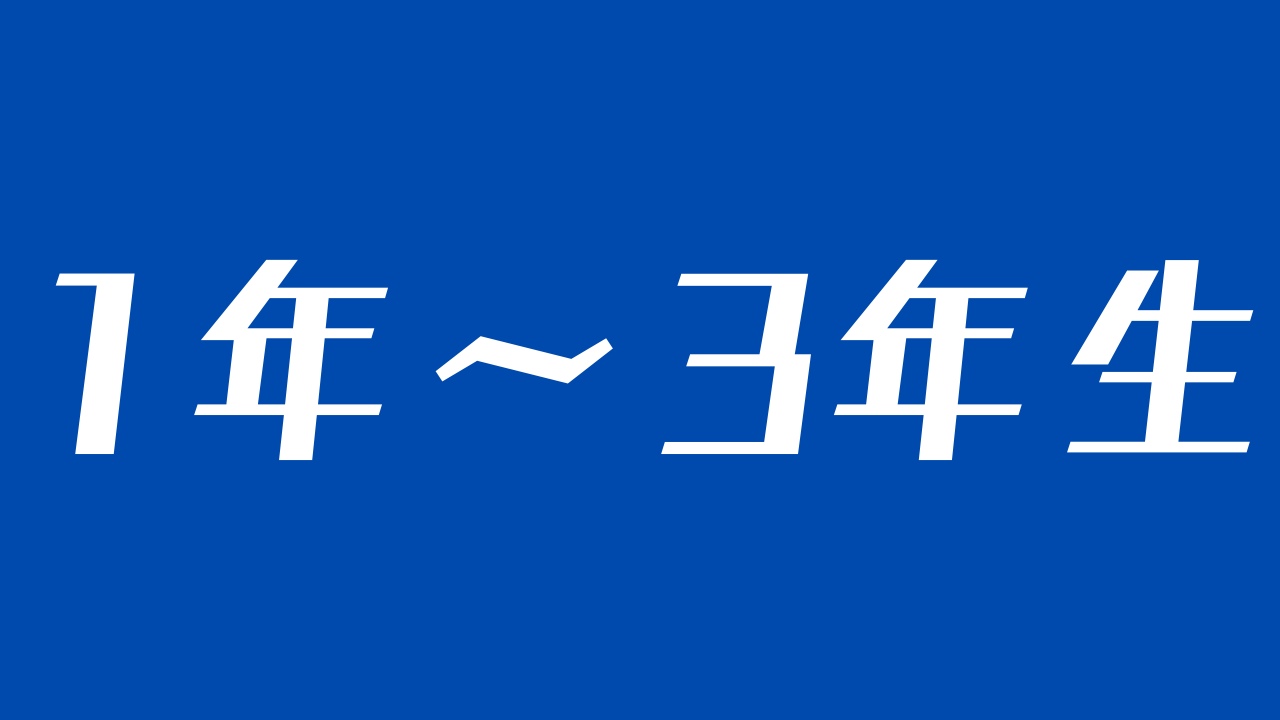







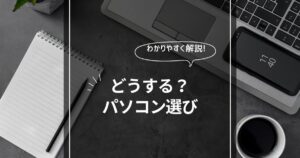
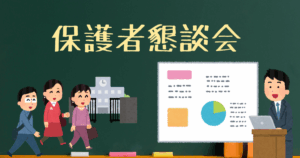
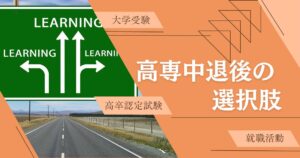



コメント