人が多く集まる閉鎖空間では、価値観や生活リズムの違いから、人間関係に何かしら問題が発生しがちです。
高専の学生寮も例外ではありません。
大切なことは「問題をゼロにする」ことではなく、「起きた問題を学生自身の力で解決し、再発を防ぐ」ことです。
高専の寮はただの住居ではなく、共同生活を通じて、コミュニケーション能力や問題解決能力を養う「教育寮」という位置づけです。
寮則を守ること以上に、話し合い・役割分担・合意形成を経験し、コミュニケーション能力や問題解決能力を育ていることを目的としています。
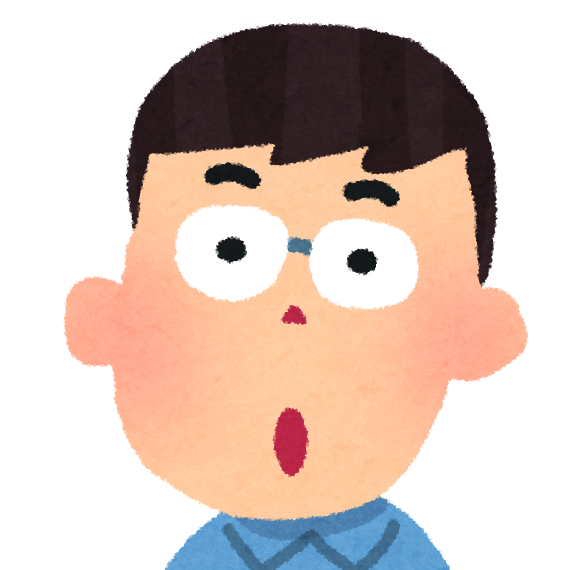 中学生
中学生寮生活って、友達とずっと一緒で楽しそう!でも、人間関係のトラブルが起きたらどうすればいいの?
本記事では、寮内トラブルがどう解決されていくか、そして保護者はどう関わるかを解説します。
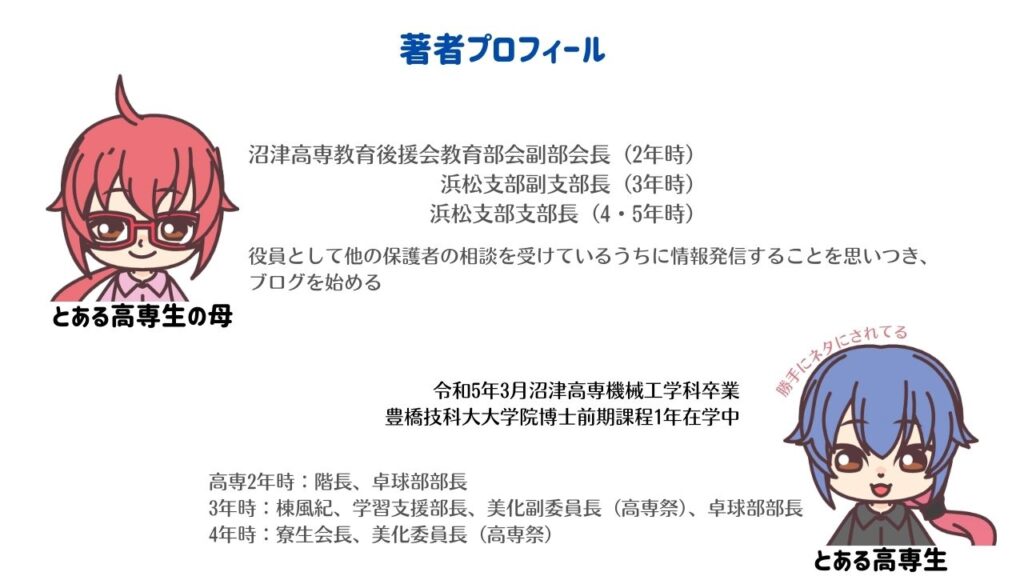
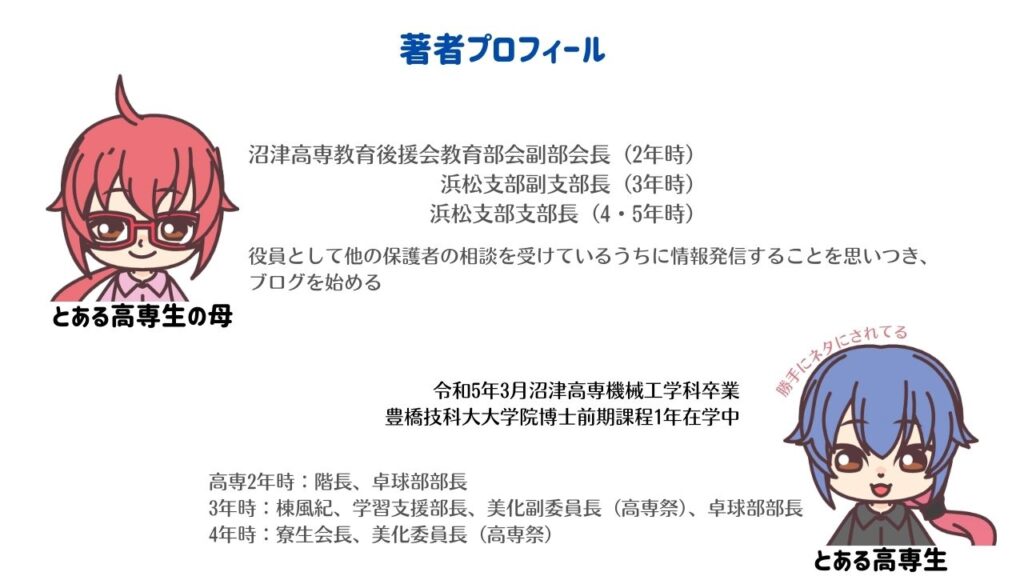
相談〜解決までの基本フロー


なにか問題が生じた時、再び問題が発生しないようにするために、当人同士の話し合いのみですべて解決されることが理想かもしれません。
しかし同様の問題が発生しないようにするためには、トラブルの情報共有と合意形成が不可欠です。
- 一次対応(階長)
同室・同フロア内の小さな行き違いは、まず当該階長が状況の聞き取りと、注意喚起やその場の合意形成を行います。 - フロアを超える場合(棟三役+全階長)
同フロア内で収まらない少し大きな問題は、棟三役+全階長で共有し、対応策を検討します。 - 寮生会・寮務主事との連携
ルール改定や配置換えが必要な案件は、寮生会で話し合い、寮務主事や学校側と連携し、決定します。 - 再発防止
関係者で何を変えるかを確認し、ルール・運用・配置を見直します。
- 実際の手順や役職名は学校により異なります。それぞれの高専にご確認ください。
- 問題の種類によって、必ずしもこの通りに行われるとは限りません。問題の種類によって、報告先が異なることがあります。
よくあるトラブル例と解決策


寮では、以下のような日常的な問題が頻繁に発生します。
- 騒音問題
- 生活習慣のズレ
- 相部屋でのすれ違い
騒音問題の悩み
- 消灯時間後の話し声
- ゲーム音・目覚まし音
- 楽器演奏
サイレントタイムの明確化、ヘッドホンの徹底、音量・時間帯のルール、起床アラームはバイブ+光に変更 など、解決策や妥協案を見つけていきます。
生活習慣のズレ
- 共有スペースの誤った使い方
- 掃除当番の不履行
- 私物放置
使い方をマニュアル化、当番表の見直しと可視化、初期教育(オリエン)を再実施などを行い、徹底します。
相部屋でのすれ違い
沼津高専寮は、一人部屋もありますが2人部屋もあります。



私のときは、1年生は必ず2人部屋だったよ。
- プライベート不足
- 相方との相性問題
相方の変更・一人部屋への変更(空き室状況や運用次第)、生活リズム表の共有などで解決を試みます。



何度部屋返しても駄目な問題児がいたんだけど、最終的に俺と相部屋にして、俺が見張っていることになった。
これも程度にもよりますが、部屋を変更して解決することもあります。
高専生は人間関係も「方程式」で解く?
これはある保護者の方が言っていたことです。
高専生は理系の子らしく、人間関係も方程式で解いちゃうんだよね~。
誰がxで、誰がy?
人間関係の変数を設定し、それぞれの行動が問題の発生確率にどう影響するのか、数学の問題を解くのごとく、論理的に分析しようと試みていることがあります。
寮のトラブルに保護者はどう関わればよいのか


高専の寮生活は、学生が自律するための良い機会です。
保護者は子どもが寮生活で直面する人間関係のトラブルに、どう向き合えばよいのでしょうか?
「愚痴」はストレス発散のサイン
子どもが寮の愚痴ばかり言っていたとしても、心配しすぎる必要はありません。
長期休暇やイベントなど、久しぶりに親子対面をしたとき、子どもはいろいろな話をしてくれます。基本的に親は聞き役に徹し、子どもの話に耳を傾けるだけで十分です。
しかし愚痴の中にちょっとした異変を感じたら、事実と感情を分けて受け止め、即断剤・即解決指示は避けるのがコツ。
違和感を覚えたのなら、一緒に問題を整理して考えてみましょう。
深刻化の兆候
愚痴ではなく、特定の人との関係について深刻な悩みや、体調不良を訴え始めた場合は要注意。
子どもが自分一人で抱え込んでいると感じたら、寮の教員や職員に相談するよう促してみましょう。



何か問題を感じたのなら、日時や場所、関係者とのやり取りなどを記録に残しておくと良いよ。こっちも対策しやすいし。
正規相談ルートの案内
問題は上記に紹介した、「階長」→「棟長」→「寮三役」→「寮務主事」といった手順を確認し、子ども自身に相談を促します。
問題によっては、スクールカウンセラーを利用するなど、他の窓口も存在しています。
保護者から相手学生やその保護者へ直接連絡することは避けます。必ず学校窓口を通します。
「退寮=終わり」ではない
寮則に則って、停寮や退寮を求められるケースがあります。
また、どうしても寮生活に馴染めなくて、通学・下宿へ切り替えることで問題が解決することもあります。
懲戒処分で退寮になってしまう場合は仕方がありませんが、寮の集団生活に馴染めないのであれば、親子でよく話し合い、通学・下宿に切り替えることをおすすめします。



できるだけ寮生活に馴染めるようにはするけど、どうしても寮生活に馴染めなくて、自宅通学に切り替える学生はいるよ。
まとめ:寮生活は成長のための「学びの場」
高専の寮生活では、時に困難な人間関係に悩まされることもありますが、それはすべて、将来社会に出た時に役立つ貴重な経験となります。
寮のメンバーとして意見をぶつけ合い、協力しあい、問題解決に取り組む中で、学生たちはコミュニケーション能力やチームワークを養い、問題解決能力を磨いていきます。
寮生活は子どもにとって、大きく成長するための「学びの場」。



話を聞いてあげるだけで問題が整理され、解決することもあります。会うたびに、子どもが大きく成長していることに驚きますね。


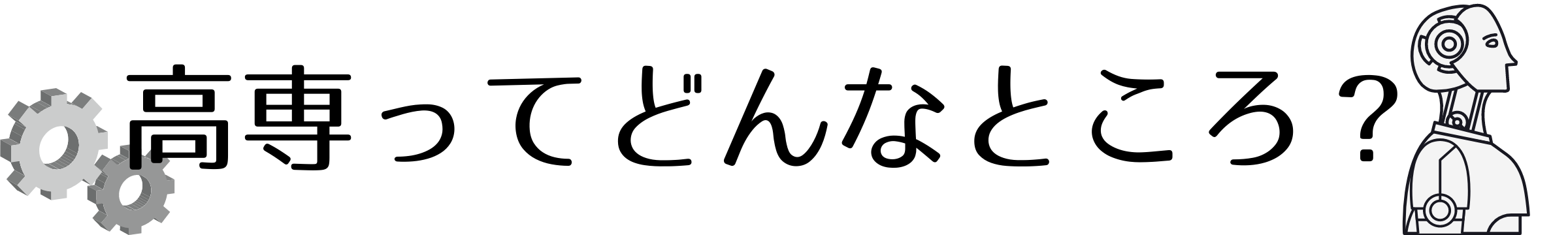

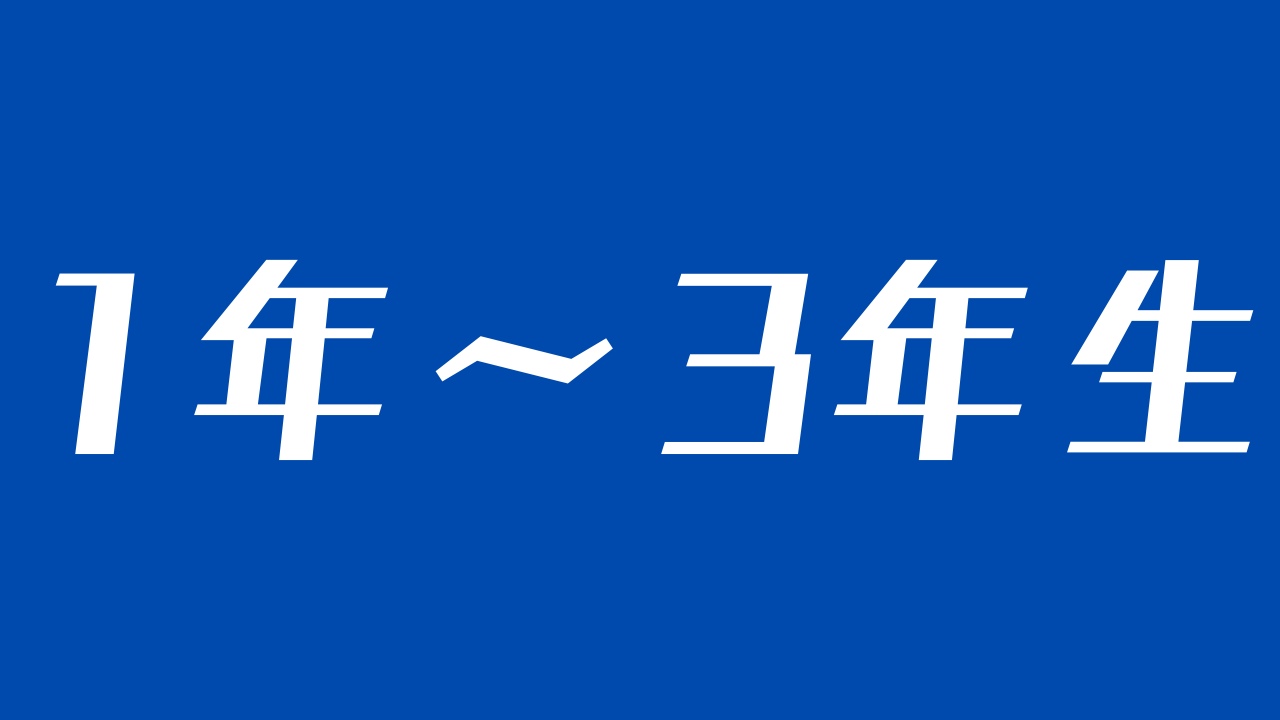













コメント